【研究者紹介】
「正解が簡単に導けない」難病に挑む
医学部 武井 正美 教授
血液膠原病内科学分野で臨床・基礎研究に従事。後進の学生には自由な発想の研究を奨励
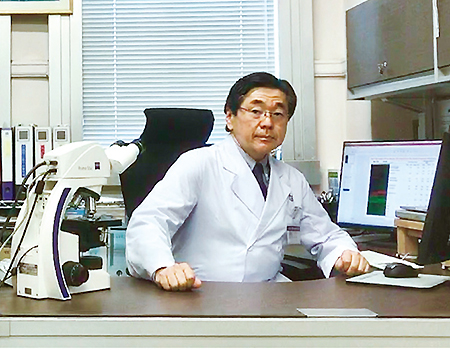
医学部 武井 正美 教授
生家は群馬県高崎市の歯科医で、父と兄夫婦と甥っ子が本学歯学部の出身、さらに愛娘は芸術学部音楽学科卒でバイオリニストという武井教授。少年時代、「お前は何をしてもいい」と言われた物理好きの次男坊は将来の道を模索するうち、「自分たちで生命を守った村」(岩波新書)や農村医療の権威・若月俊一の著書に啓発され、臨床医の道を選択した。
「元々は研究志向で大学に残りました。今は製薬会社が開発した新薬の治験を行う臨床研究を若い人たちに任せて、自分は病気の根本原因を追究する基礎研究が中心です」と武井教授。とはいえ、専門の血液膠原病内科学分野ほか内科学系全体の主任教授として学生の教育も臨床もおろそかにはできない立場。「使える時間は限られているので、よそがまだ手を付けていない、オリジナリティーの高い研究に絞ってやるように心掛けている」そうだ。
患者のための研究室
昨年「オプジーボ(がんの免疫治療薬)」でノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑氏は「自分が大学院生の頃から尊敬している先生」という。
「本庶先生は基礎研究をきちんとやる方で、オプジーボ以前にも、もっとすごい免疫の研究をされている。若い人にも研究の面白さを分かってほしいと思って、座学の折にはよくその話をしています」
臨床の専門医制度が始まって以降、若い人たちにとってはその資格を取ることが一番の目標となり、基礎研究に興味を持つ者は少なくなったそうだが、それでも武井教授は後進の研究者の出現に期待を寄せる。
「若い人には常に『何でもいいから好きなものを見つけて、責任を持って取り組むことが一番大事だ』と言っています。基礎研究はどういうことに興味を持つかが重要。好奇心を持って取り組めるものでないと苦痛なだけですから。今は科学全体が大きく変わろうとしている時機で、医学も若い人が自由な発想で行う研究を認めていかないと、今後新しいものは出てこないと思います」
ちなみに「責任を持って」の「責任」とは、医療者として患者さんに対して、社会人として同僚、仲間に対してのものだという。
「臨床の研究室は患者さんのためにあります。どんな状況でも、患者さんがつらい思いをしているときに臨床を放り出すわけにはいかない。最終的には自分の患者さんの診方に影響を与える(新たなより良い療法を見つける)ような研究でなければいけないのです」
ストレスが免疫に関与

日本リウマチ学会で初めての発表を終えた後輩たちと(2015年4月、名古屋)
最後に、武井教授の専門分野の一つである膠原病について尋ねた。
膠原病とは免疫システムの誤作動で起こるさまざまな疾患の総称で、「関節リウマチなど一般的なものでも原因が不明で、一つでも分かればノーベル賞を取れるレベル」という原因が解明されなければ、完治に至る治療法も確立されない。
「膠原病は先行きの予想ができない、選択した治療法がその患者さんに適しているのかどうかも分からない難しい病気です。自分の研究室チームでは、一人でも反対意見のある治療法は選択せず、全員の意見が一致するまで徹底的に話し合います」
今も各所でさまざまな研究が続いているそうだが、武井教授は「ストレスなど精神的なものが免疫の指標に大きく関与することを、過去の臨床で何度も経験した」という。
「ですので自分の好きなことをして大いに楽しんだり笑ったりすることが、膠原病には一番の予防法かもしれません。要はストレスをためないことですが、言うは易し行うは難しで、本人には自覚のないストレスというのもありますからね」
正解が簡単に導けないからこそ研究のしがいもある、と武井教授。今後の研究成果に期待したい。
医学部
武井 正美(たけい・まさみ)教授
昭和55年本学医学部医学科卒。60年同大学院医学研究科臨床系内科学Ⅰ課程修了。博士(医学)。
主な研究分野は臨床免疫学、膠原病・アレルギー・血液内科学、ウイルス学。
平成24年4月に医学部内科学系血液膠原病内科分野主任教授および附属板橋病院血液膠原病内科部長に就任、内科学系主任教授兼務、現在に至る。本学医師会会長。群馬県出身。63歳。

