ロハス工学による「産学官民」の建築・まちづくり
新しい木構法と仮設住宅の再利用でキッズデザイン賞優秀賞を受賞
工学部建築学科 浦部智義教授
LOHAS(Lifestyles of Health and Sustainability)は、健康で持続可能な生活スタイルのことで、工学部ではそれを工学的に実現することを目指す「ロハス工学」を教育・研究のコンセプトとしている。一昨年の水害で解体を余儀なくされたが、ロハスによる生活スタイルを支える住環境づくりを目指す「ロハスの家」や東日本大震災からの復興活動などのプロジェクト経験、自然の浄化作用を活用した排水処理システムによる「ロハスの花壇」など工学部としての研究蓄積を生かし、ロハス工学の社会での見える化を進める建築学科・浦部智義教授。今年9月に発表された「第15回キッズデザイン賞」で、浦部教授をリーダーとするグループが建築計画・設計した施設「スマート ウェルネス タウン ペップ モトマチ」が優秀賞・少子化対策担当大臣賞を受賞した。

「スマート ウェルネス タウン ペップ モトマチ」の医院棟の外観。木の壁がガラス越しに見え、通りに明るさと温かみを加えている
医師のロハス工学への賛同がプロジェクトの始まり
ロハス工学の考え方に賛同した福島県郡山市にある菊池医院の菊池信太郎医師は、震災によって自宅等にこもりがちな福島の子どもたちの発育を考え、屋内の遊び場をつくりたいと浦部教授らと一緒に自治体に掛け合ったり、考え方を共有したりしていた。その頃からのつながりで、菊池医院の建て替えに当たり、「ぜひロハス工学の考えを取り入れた建物にしたい」ということで浦部教授に声掛けがあり、小児科と病児・病後児保育機能が入る医院棟と、薬局・オフィスや子どもの遊び場からなる建築群を造るプロジェクトが始動した。

新しい木構法で造られた多目的スペース

まちに開かれた木質空間
医院棟は、診療所らしくない建築を目指し、木質の内装や外部(通りやまち)に対しても大きく開かれた建築デザインとし、通りや周辺に木の温かみや人のにぎわいが表出されている。多目的室や大きめの待合空間など、診療所としてだけでなく、地域の方々の利用も含めてさまざまな用途に応じてフレキシブルに使用できる場所・空間を計画し、実現している。そうした柔軟性は、時間がたつ中で求められる機能の変化に対応する上で必要になるものであり、ロハスの建築に深く関係するサステナブルな建築にするための大事な要素となっている。実際、少子高齢化社会で子どもが少なくなっている中で、「診療だけで地域貢献になるのだろうか」という菊池医師の考えで、休診日には医院棟から薬局・オフィス棟の駐車場までを開放して地域と協働したイベントを行い、施設全体を多目的に活用もしているという。
また、建築方法では、浦部教授もメンバーである「縦ログ構法研究会」で開発や普及を進めている縦ログ構法といった新しい木構法を取り入れている。これは接着剤を用いず、かつ大きな機械を導入しなくても地元で製材できる木パネルを用いた木構法であり、木の地域循環といったロハス的な視点のみならず、木の建築としても特徴ある空間づくりにつながっている。
東日本大震災後に建設したログハウス型仮設住宅を移設再利用
2011年3月11日に発生した東日本大震災とその後の原発事故の影響で、福島県では16,000戸以上の仮設住宅が必要とされていた。福島県では、その内8割強に当たる約13,000戸が県による買取り方式で、かつ、福島県では震災前から豊富な地元の森林資源を生かして木造住宅を造る動きが盛んだったこともあり、多くが木造で建設された。また、それらの仮設住宅は供与期間後の再利用を視野に入れていた。その仮設住宅の建設には、県内の団体が数多く参加したが、浦部教授と研究室は、地元の建築業者と協働して、再利用しやすい工法であるログハウス型の仮設住宅を造る提案で参画し、600戸の仮設住宅を建設した。なお、そのログハウス型の仮設住宅団地においては、福島県での避難が長期化することを見越し、住戸配置なども、従来の仮設住宅には見られない工夫がされている。
浦部教授らのチームは、供与期間後のログハウス型仮設住宅の移設再利用についてもフォローしているが、このプロジェクトで初めて、平屋の木造仮設住宅を2階建てにすることを試みている。「仮設住宅は平屋ですが、初めて2階建ての再利用をしました。その磨きは研究室の学生にも協力してもらいました。新しい木構法の開発・実践も含め、県内の企業と産学連携で取り組めたことがよかった」(浦部教授)

ログハウス型仮設住宅を移設再利用した薬局・オフィス棟。中央には、キャンパス内にあったロハスの花壇が移設されている
これらの建築群を、建築・空間のカテゴリーで「第15回キッズデザイン賞」に応募したところ、優秀賞・少子化対策担当大臣賞の受賞となった。産学連携での活動をベースに、ロハス工学の視点に基づき開発した新しい木構法による建築である診療所空間、仮設住宅の再利用といった、健康で持続可能な地域づくりに寄与する、子どもの医療から健康維持、産み育て支援、交流促進を一体的に捉えたコンパクトな建築デザインが、今後、各地で必要とされる視点だとして高く評価された。地域医療と工学を融合させた健康で持続可能なまちづくりに貢献する建築デザインや取り組みは、福島発のモデルとして全国展開されることが期待されている。

移設再利用したログハウスの内側を磨く研究室の学生の様子

遮熱塗料のロハスの道(写真左側)と木塀。街並みを美しく見せる仕掛けだ
新しい医療福祉施設から、ロハスのまちづくりへ
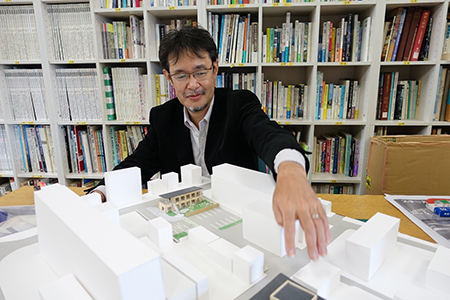
ロハスに込められている、健康で持続可能な生活スタイルのうち、工学ではどうしてもエネルギー的な側面など持続可能(サステナブル)な考え・実装に偏りがちなところ、この新しい医療福祉施設の建築群づくりによって、医療や子どもの遊び場といったヘルスそのものに関わることができたという。
また、薬局棟にはロハスの花壇や遊び場を設け、子どもを遊ばせることで、処方の待ち時間を有効に活用できるだけでなく、待合室にいることで感染リスクもある昨今、これまでの病院の概念、在り方を変える建築群になっている。
その他、県産木材を多用しながら環境装置としても木を利用したり、接着剤を使わないことで解体の際は再利用を可能とする建築など、これまでのロハスの家群では扱えなかったことを実装している。
「病院ではなくても成立する、病院らしくない開かれた建築でまちの活性化を目指しているのがポイントです。その小さな建築造りが、まちを大きく変えることになれば、まちなか再生につながり、サステナブルなまちづくりになるかも」と浦部教授。
コロナ禍により変化する生活スタイル。SDGsに先駆けて取り組んでいた工学部の「ロハス工学」が、実際に地域の健康で持続可能な生活に寄与し始めている。今後、「ロハス・コミュニティ」へと発展し、全国へ広がりを見せることも期待される。
- 関連情報

