我、プロとして
Vol.20 板坂直樹 氏【前編】
株式会社CAVIC 代表取締役社長(1990年文理学部卒)
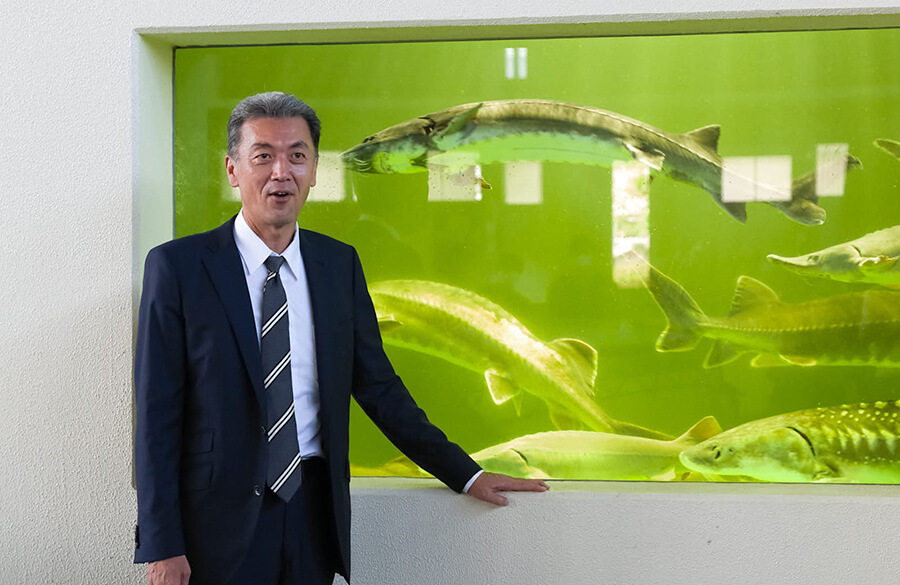
日本発「キャビア」づくり
愛する地元・香川県引田町から世界へ
「キャビア」と聞いて、産地を日本と答える人はまだ少ないだろう。カスピ海原産、銀色の缶や瓶に入り、結婚式の食事など限られた場面で口にする世界三大珍味。歴史を遡ると紀元前や中世ヨーロッパ、カスピ海発祥といれ、かつてはすぐに腐ってしまうキャビアは漁業を営んでいる漁師の食べ物だったという。人々の味覚を虜にするキャビアは保存方法の発達ともに、貴族の間に広まり上流階級の間に貴重で高価なものになっていった。
歴史と格式あるキャビアを日本でメジャーに、そして先を行く世界と対等、いやそれ以上にすべく奮闘している人がいる。株式会社CAVIC・代表取締役社長の板坂直樹氏だ。
校長室は社長室、家庭科室は加工場に。
高松駅からJR高徳線・特急うずしおに揺られること45分。瀬戸内海を望む四国の東端、徳島との県境に近い引田町(現=東かがわ市)に、板坂氏の母校で現在は廃校になった旧引田中学校が物語の舞台。
引田の町は、世界で初めてハマチ養殖に成功した地で、その技術は後に「近大マグロ」に通ずる。また、和三盆(砂糖の一種)の発祥地と知られ、もともとは「三盆糖」と呼ばれていた。「三盆」の由来は諸説あるが、出荷港が香川の三本松であったからという説もある。
そこに第三の特産として旗を揚げた「瀬戸内キャビア」。
学校の特性を生かした施設で、キャビアづくりは行われている。

学校の特性を生かした施設でのキャビアづくり
父・信定さんから継いだ内装業を主とする大協建工株式会社の二代目に36歳で就いた。
本社は高松だが、人口6,500人ほどの地元・引田出身者として、廃校となった母校を活用できないかと話しを持ちかけられたのが2012年だった。
記念館でも建てるか、倉庫として使うかと言われたが、
「商売人が生産性のないものつくったらアカン」
と、断固として首を縦に振らなかった。
当初は乗り気ではなく、すぐに頭に浮かんだ広い校庭に太陽光発電を設置するに留まった。
しかし、ある日、板坂氏いわく「(天から)降ってきた」のが、自身が少年時代に水泳部で泳ぎ明け暮れたプールを活用した養殖。
しかも、引田の特産であるハマチの養殖ではなく「チョウザメ」。キャビアに目を付けた。
突然のひらめきだった。
こうして、内装業を手掛ける大協建工株式会社はキャビアづくりの新事業に着手する。

チョウザメ(蝶鮫)はサメとついているが、サメではない。
チョウザメ目チョウザメ科の回遊魚で、外観がサメに似ていて背中のウロコが蝶の羽に似ていることから名付けられたとされている。
2億5千年前から生息し、海と淡水の両方で棲むことができる。産卵時は河川を遡上する習性がある。
香川県は他県と比べると雨量が少なくカラッとした気候で、学校の側を流れる小海川が枯れたのを子供のころから見たことがない。自分の経験がひらめきにつながった瞬間だった。
そこで試しに地下水を掘ってみると、ミネラル分豊富な天然水が湧いて出た。
その源泉を掛け流しで1,000tの水をプールに汲み、キャビアの養殖がスタート。
しかし、問題が起こる。
立ち上げ当初のある日、協力を得ていたハマチ養殖のノウハウがある地元の漁師さんから、連絡が入った。
「遮光幕を張ってくれ」
それもそのはず、遮るものがない屋外の50mプール。
裏手にある翼山もせいぜい250mほど、日陰は全くなかった。
水温の上昇による飼育水の異変にいち早く気が付いた漁師さんに対して、温度上昇を防ぐ、遮光幕を張らなければならない。建築業の仕事柄、ネットを張るために、支柱の強度計算が重要だと気付いた。
「ちょっと待ってくれ」強度計算が先だ。
支柱の強度計算をして50mを覆える遮光幕、容易なことではないとすぐに計算できた。
そう答えた翌日には、すでに遅かった。水温上昇で植物性プランクトンによる赤潮が発生した。水面は赤い、青ざめた。
急いで本業の高松本社から職人さんを呼び、隣の体育館にチョウザメを移動。幸い一匹も死なずに済んだ。
失敗から少しずつ学んでいった。
こうして、「水泳」「プール」「養殖」というストーリー設定は書き換えられ、屋根はある、鳥害に遭わない、戸締りができる利点のある「体育館」の床一面に水槽を置き、キャビアづくりの第二幕が始まった。
卵嫌いが奏功した自慢の品質

加工を行うのは家庭科室。学校設備がキャビアづくりにマッチしていた。
廃校再利用の相談を受けてから1年後の2013年。本格的に体育館にてチョウザメの養殖がスタートしたものの、チョウザメはキャビアとなる魚卵を抱卵するまで7年かかるとされていた。
「さすがにリードタイムが長すぎる」
そこで生育途中の個体、すでに抱卵している個体も買い付け、1年目から採卵、生産を開始しブランディングを図った。
キャビアと聞いて塩辛さをイメージされる方もいるかもしれない。
塩辛さは保存と物流の問題で、本来の原産地で食べられていたキャビアはそこまで塩味が強くない。
また、塩の浸透圧の関係で、缶の中で魚卵がつぶれて液体(ドリップ)が出ると生臭くなる。
初期の頃、展示会に出展した際にロシア人から「本当のキャビアは塩味がここまで強くない。それと、プチっとした固い食感は品質が低い」と聞いた。
目から鱗だった。
良いキャビアは口に運ぶととろける。
確かに自分も魚卵が苦手で、その理由はドリップの生臭さと固い食感だった。
良い魚卵はプチプチしてはいけないのだ。
そこから、キャビアづくりは研究となり、必ず板坂氏が味見をし、出荷の合否を判断する。
試食の数が1日150個体分になることもあった。
苦手な魚卵をそれだけの数を食べることは大変だが、判断基準を曖昧にしないためにも、今も味見は一人でしている。
採卵のタイミング、チョウザメの扱い方、水温、水槽の掃除まで些細なことまでこだわった。
そして6年後の2019年、予定よりも少し早く稚魚から育てたチョウザメが抱卵。
今では徳島県・鳴門市にも第二養殖場を構え、合わせて1万3千尾近くのチョウザメを飼育するまでになった。
5回断った謎の電話。「ゴ・エ・ミヨ」とは

1969年に創刊したレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」の受賞式
ある時、会社に電話が入った。
「ゴ・エ・ミヨです」
板坂氏に取り次ぐように言われるが、何のことか分からず、銀座に出店したキャビアを扱うレストラン「17℃」のことだと思い、店に取り次いだ。
そこに、店長から板坂氏に電話が入る。
「社長、店ではなくキャビアです。キャビアが受賞しました」
ゴ・エ・ミヨとは、ミシュランと並ぶ強い影響力を持つフランス発祥のガイドブックだった。
その『ゴ・エ・ミヨ 2020』の日本版で、テロワール賞を受賞した「瀬戸内キャビア」。
テロワール賞は、その年に日本中のありとあらゆる食材の中から2社だけ受賞できる。優れた食材であることと食材を通して、生産地の風土や文化を、信念を持って伝える生産者に授与される、誉れ高い賞だった。
料理人界隈では、ミシュランよりゴ・エ・ミヨに選ばれることを名誉とするという。
板坂氏自らの地道な研究、営業が結実し手にした日本の食材の頂点。
世界に認められた「瀬戸内キャビア」が、次のステージへ上がる朗報だった。
日本人の味覚で育て、世界一美味しいキャビアへ

個体ごとに魚卵の色が違うキャビア。その世界は奥が深い
そもそも日本の食材、食文化としては無かったキャビアだが、同じように海外から入ってきた食文化が、日本人の味覚で磨き、日本発で世界に羽ばたいていった食材がある。
牛肉、黒毛和牛だ。
「今では海外に輸出して、現地の牛肉の5倍の値段で売られているそうです」
同じように日本人の味覚で育て、日本発で世界に評価される“キャビア”にするのが、板坂氏の次なる目標だ。
「ヨーロッパの真似をしていてはどうしても二番にしかならない。だから、日本人の味覚で育てるキャビアを世界一美味しいキャビアにしたい」
実際に世界一のキャビア商社が、「瀬戸内キャビア」を美しい水の美しい味がする、と褒めてくれたことがあった。
世界のグルメ家たちが、板坂氏がこだわった「瀬戸内キャビア」の一粒一粒に舌鼓を打つ日も近い。
【中編】では板坂氏自身のストーリーをお伝えする。
<プロフィール>
板坂直樹(いたさか・なおき)
1968年生。香川県引田町(現:東かがわ市)生まれ。1990年文理学部卒。
本学卒業後、大阪の大建工業株式会社で管理者=番頭の仕事を学び、36歳で父が興した内装業の大協建工株式会社の代表取締役社長に就任。2012年から廃校になった母校・引田中学校の再利用としてチョウザメの養殖を始め、キャビアづくりを手掛ける。
「瀬戸内キャビア」の商品はフランスのレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」のテノワール賞を受賞。銀座にキャビア・バー「17℃(ディセットゥ・ドゥグレ)」を構える。
座右の絵は「洞窟と頼朝」(作・前田青邨)。

