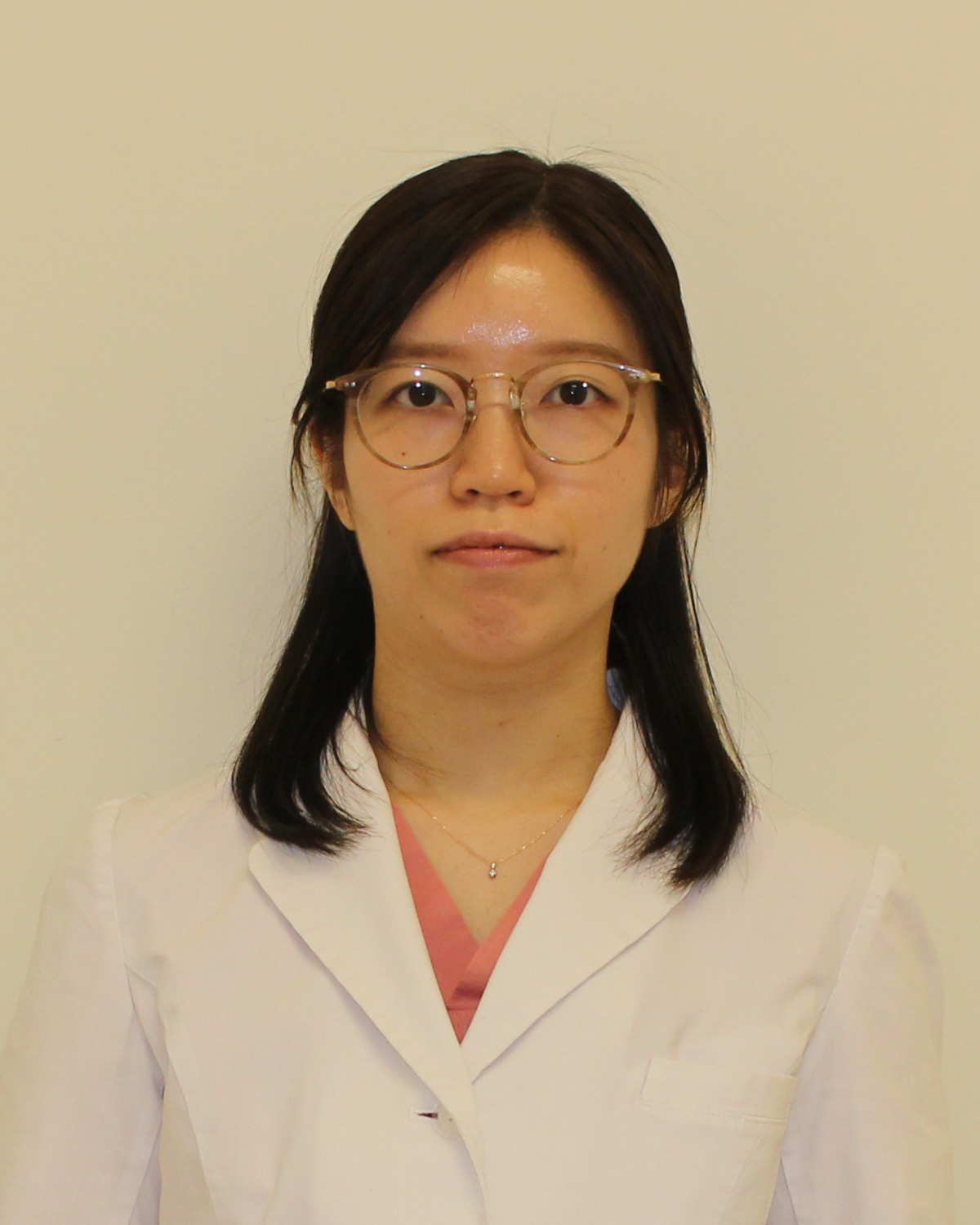①大腸の構造
大腸は1.5~2m程度の長さの臓器です。盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸という順に食べ物が流れ、肛門から便となって排泄されます。盲腸の端の細長い突起が虫垂です。盲腸と虫垂は異なるものです。‘盲腸’とよばれている病気は、この虫垂に炎症が起こる病気で正式には「虫垂炎」と言います。
②大腸壁の構造
大腸の壁は、5層で構成されています。内側から順に粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜とよばれます。
③大腸の役割
大腸は、小腸から流れてくる液状便から水分、脂肪酸、ナトリウムなどを吸収します。盲腸から肛門に運ばれる過程で固形便へ変化していきます。
④大腸癌とは
大腸の細胞が異常に増殖して塊状になったものです。浸潤や転移を起こす危険性がない良性腫瘍と浸潤や転移を起こす悪性腫瘍があります。悪性腫瘍のことを大腸癌と呼びます。
⑤大腸癌の形態
大腸癌は見た目の形態から5つに分類されます。
- 0型-表在型:さらに隆起型、表面型に分類されます。
- 1型-腫瘤型:塊状の腫瘤を形成します。
- 2型-潰瘍限局型:境界がはっきりした潰瘍を形成します。
- 3型-潰瘍浸潤型:境界がくずれた潰瘍を形成します。
- 4型-びまん浸潤型:癌が不規則に広がります。スキルス型と呼ばれることもあります。
- 5型-分類不能
⑥大腸癌の広がり
大腸癌は時間経過とともに、大きくなり、転移により全身に広がる危険性があります。
広がり方は4腫瘤に分類されます。
- 浸潤:腸の内側から外側へ向かって大きくなり、腸を越えて周囲の臓器へ浸潤していきます。
- リンパ行性転移:血管のように体中に張り巡らされたリンパ管の中を癌細胞が流れて転移していきます。近くのリンパ節から遠くのリンパ節へ一定の傾向を持って広がっていきます。
- 血行性転移:血管を通して癌細胞が全身の他臓器に転移していきます。大腸の血流はまず肝臓に流れるため、血行性転移として肝転移が最も多くなります。それに続いて血行性転移が多い臓器は肺です。骨転移や脳転移を起こすこともあります。
- 腹膜播種:種がまかれるにように腹腔内(お腹の中)に散らばりながら広がる転移です。
⑦大腸癌のステージ
大腸癌の進行度を表す基準としてステージ(病期)分類があります。
- ステージ0が最も進行度が低く、ステージIVが最も進行度が高い状態です。
- ステージ0:粘膜内にとどまる癌
- ステージI:大腸の壁(固有筋層)までにとどまる癌
- ステージII:大腸の壁の外に浸潤している癌
- ステージIII:リンパ節転移をきたした癌
- ステージIV:血行性転移または腹膜播種がある癌
⑧大腸癌の治療
主に3つの治療を中心に行われます。
- 内視鏡治療:リンパ節転移リスクの極めて低い早期癌に対して行うことができます。
- 外科手術:開腹手術と腹腔鏡手術、経肛門的な局所切除の3つの方法があります。開腹手術と腹腔鏡手術では周囲のリンパ節を同時に切除することができます。
- 化学療法:主に外科手術で完全に切除できない場合における癌の進行抑制や、外科手術後における癌の再発予防を目的として抗癌剤投与を行います。
⑨当院での大腸癌および大腸ポリープの内視鏡治療
大腸内視鏡検査は本来、大腸の中を観察し、病気をみつけるための検査方法です。その内視鏡を用いて、大腸癌や大腸の良性ポリープを切除する方法のことを内視鏡治療と呼びます。
内視鏡治療として主に3通りの方法があります。
- ポリペクトミー:比較的小さなポリープに対して、ポリープ根本に金属の輪(スネア)をかけて切り取ります。必要に応じて高周波電流を流して焼灼を行います。
- 内視鏡的粘膜切除術(EMR):まずポリープの下(粘膜下層)に液体を注入して、ポリープを持ち上げます。そして金属の輪(スネア)をかけて、高周波電流を流し焼灼しながら切り取ります。
- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD):ポリペクトミーやEMRで一度に切除が難しい大きな早期癌に対して用います。腫瘍の下(粘膜下層)に液体を注入して、腫瘍を持ち上げます。そして、電気メスを用いて腫瘍の下を剥離することで腫瘍を残すことなく切り取ります。
※当院ではこれらの内視鏡治療を原則2名以上の医師(消化器内視鏡専門医が1名以上)が協力して行います。
※当院では安全性の面からポリペクトミー、EMR、ESDいずれの治療も原則入院下に行っております。