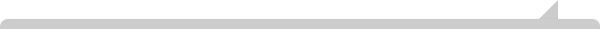写真学科
写真技術と芸術的教養・知識を身に付けた
写真のプロフェッショナルを養成

学びの特色
- 3本柱のカリキュラムで広く、深く写真を学ぶ
- 作品展など学生の制作発表の場も充実
- 写真界の第一線で活躍する写真家を招いた講義
Q 写真学科で何をする?
写真技術を修得するだけでなく、幅広い芸術的教養と知識を身に付けた写真家を目指します。表現技術を学ぶ実習、制作のための技術理論、表現や研究を行うための表現理論という3本の柱で構成されたカリキュラムで写真に関する技術と理論を学びます。
Q どんな未来が待っている?
各業界に適した専門的な実習や講義で身に付けた技術・知識を生かして、新聞社や雑誌社、広告代理店や写真スタジオなどで多くの卒業生が活躍しています。芸術性を究め、写真作家として活動する卒業生や制作を通じて培ったコミュニケーション力や表現力を生かした職業に就く卒業生もいます。
ゼミテーマ(一部抜粋)
コマーシャルフォトグラフィ/ストーリーテリングから考える写真/自身の「軸」を発見/ルポルタージュフォトの実践/現代の表現としての写真作品制作/いま,ここに生きるためのコンセプチャル写真術/写真の伝統と創造性/写真の保存/想像し,創造する~気づきの写真制作へ/「写真」について考える/ドキュメンタリー写真と写真の社会性を理解/作品制作とアート・フォトグラフィー/自然風景・都市風景・スナップ/伝える・伝わるフォト・ジャーナリズム/フィールドワークの写真術 写真を 「撮る」 「見る」 「考える」そして「見せる」
映画学科
デジタル技術の進歩で門戸が広がる
映画・映像業界のスペシャリストを養成

学びの特色
- スペシャリストを目指した4つのコース
- 理論や歴史、研究方法、多様な表現技術を学ぶ
- 国内外の映画祭などにも積極的に参加
Q 映画学科で何をする?
時代とともに進化する映像文化を新たな視点で捉え、芸術創造と情報伝達の両面から探究。1年次から[映像表現・理論][監督][撮影・録音][演技]の4つのコースに分かれ、それぞれの目的に適した独自のカリキュラムのもとで学修し、映画・映像界のスペシャリストを目指します。
Q どんな未来が待っている?
それぞれのコースで身に付けた専門知識や技術を生かし、評論家や研究者、シナリオライター、映像作家、映像技術の専門家、俳優など映画や放送業界に携わっている卒業生が多くいます。フリーランスとして活躍するだけでなく、映画、アニメ、テレビなどに関連する企業に就職しています。
ゼミテーマ(一部抜粋)
卒業論文/卒業研究/卒業制作(シナリオ)/卒業制作(監督)/卒業制作(撮影)/卒業制作(録音)/卒業制作(演技)
美術学科
人間の本質を探り、豊かな創造力で
新しい芸術を創造する美術家を養成

学びの特色
- 専門的に美術を学ぶ2コース4専攻
- 充実した制作実習で知識と技術の両面を修得
- 学外とコラボし、社会と美術の関わりを学ぶ
Q 美術学科で何をする?
人間が本来持っている豊かな創造力を育て、新しい芸術の創造を目指す人材の育成を教育の理念としています。演習や実習・創作活動と並行し、充実した理論・歴史部門、研究部門の科目も設置。理論と演習の相互学修から美術作家や広く芸術に関わる人材を目指します。
Q どんな未来が待っている?
美術作家として活動するほか、一般企業で美的センスを生かした仕事に就く卒業生もいます。また、中学・高校(美術)、高校(工芸)教員免許、学芸員資格も取得可能で、教員・学芸員として活躍する卒業生が多いのが特長です。免許取得に関わる博物館実習など、学外授業もサポートしています。
音楽学科
広い視野と豊かな人間性、
確かな技術を備えた一流の音楽人を養成

学びの特色
- 6つのコースでそれぞれの専門性を高める
- 第一線で活躍する講師陣のマンツーマン教育
- 徹底した実技演習で技術と豊かな人間性を養う
Q 音楽学科で何をする?
[作曲・理論][音楽教育][声楽][ピアノ][弦管打楽][情報音楽]の6コースに分かれ、創造、教育、演奏という柱のもと広い視野と豊かな教養を培います。演奏や創作だけでなく、哲学、美学、文学といった諸関連芸術分野も学ぶことで、次世代の音楽芸術を担う人材を目指します。
Q どんな未来が待っている?
卒業後は演奏家や音楽家だけでなく、音楽の知識を生かし楽器製造会社やレコード会社、エンターテインメント企業や企画会社などへの就職も可能です。そのほか中学・高校(音楽)教員として活躍する、または大学院へ進学するなど幅広い選択肢があります。
ゼミテーマ(一部抜粋)
情報技術を使った音楽作品制作/音楽ビジネスの分析や企画演習/電子楽器やアプリケーションの開発/音楽音響心理の研究/メディアアートの制作/西洋クラシック音楽/音楽美学/近現代の音楽/日本の伝統音楽/民族音楽/音楽マネージメント/音楽と映像/歌詞と音楽/「エモい」と感じる音の要因とその定義/起床時における快適な音環境のデザイン/作曲経験者と未経験者の音楽のうけとり方の相違について
文芸学科
“書くこと,発表すること”を中心として、
実践の中で文芸的な創造力と表現力を磨く

学びの特色
- 実践を通して創造や表現、手法を学ぶ
- 幅広い文学ジャンルを深める充実した演習・講義
- 各界から著名な講師を招いての特別講座
Q 文芸学科で何をする?
学びの対象領域は、詩・小説・戯曲・批評をはじめ広くジャーナリズムの世界にまたがる文学研究です。表現活動を通して、主体的に文芸そのものを理解し、文芸的な創造力と表現力を養います。また、独自の雑誌制作の中で、企画、創作、編集から印刷までのプロセスを実践的に学びます。
Q どんな未来が待っている?
編集者やライターとして出版・印刷会社、企画宣伝やイベント制作に携わる広告会社などの企業への就職のほか、大学院への進学、教員などの選択肢があります。中学・高校(国語)教員を目指す教職課程や図書館司書の資格を得る司書課程が開講されています。
ゼミテーマ(一部抜粋)
文芸創作(小説、シナリオ、エッセイ、詩、短歌、俳句、漫画など)/文芸評論/編集
演劇学科
舞台創造の力で自らの道を切り拓く
プロフェッショナルを育てる

学びの特色
- 4コース10専攻の広く深い学び
- 理論と実践の2分野を組み合わせて学ぶ
- 第一線のプロの指導を受ける
Q 演劇学科で何をする?
舞台創造の力を生かしてさまざまな分野でプロとして活躍するために必要な歴史を学んだり、専門領域の演習や実習が多数用意されていたりと“理論”と“実践”のバランスに配慮した授業を受けることができます。さらに「総合実習」などの授業を通して、舞台芸術に関する高い技術と創造力を身に付けます。
Q どんな未来が待っている?
公共・民間劇場やプロダクションといったエンターテインメント産業の多様な分野で多くの卒業生が活躍しており、演出家や舞台監督、企画制作者、劇作家、ライター、俳優、美術デザイン、音響オペレータ̶などとして、学科で得た専門知識を生かしています。そのほか、一般企業に進む人も多くいます。
ゼミテーマ(一部抜粋)
劇作/演出/演技/舞台美術/照明/音響/舞台監督/企画制作/日舞/洋舞/作家作品研究/伝統芸能/現代演劇/応用演劇/アートマネジメント
放送学科
情報文化の発信者に求められる
個性豊かな創造力・表現力を育む

学びの特色
- 1年次から実習を軸に7つの分野で専門的に学ぶ
- 放送に関わる幅広い教養と専門分野の知識を究める
- 分野の枠を超えて表現者としてのスキルを身に付ける
Q 放送学科で何をする?
理論と実践を総合的に学びながら、個性豊かな創作能力を育み社会への発信力を養います。数多くの演習では、放送メディアに関する専門知識と情報伝達技術を身に付けます。また、分野の枠を超えた演習を通して番組企画構成、コピーライティング、取材調査などを学び、表現者としての幅を広げます。
Q どんな未来が待っている?
卒業後はテレビ局、ラジオ局、番組制作会社、広告代理店、広告制作会社などに多く就職しています。また、4年間で学んだそれぞれの専門性をさらに磨き脚本家、放送作家、アナウンサー、タレントとして活躍している卒業生もいます。
ゼミテーマ(一部抜粋)
論文(テレビ分野、ラジオ分野、広告・CM分野、配信、その他放送に関わるテーマ)/映像作品/音響作品/脚本/朗読発表/アナウンス/ルポルタージュ
デザイン学科
デザイン力はもちろん、豊かな感性と
鋭い洞察力を持ったデザイナーを養成
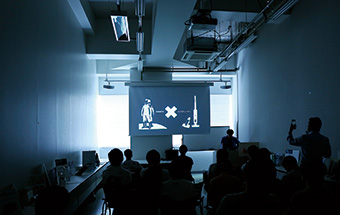
学びの特色
- 理論と実践をベースに感性と制作技術を養う
- デザイン思考と専門的技術で問題解決力を培う
- 学外でプロにデザインの実践過程を学ぶ
Q デザイン学科で何をする?
広告やポスター、情報メディア、家庭用品、電気製品、自動車、家具、住宅などあらゆるジャンルのデザインを総合的に学び、幅広い知識と高度な専門性を持ったデザイナーを目指します。デザイン思考と専門的技術でさまざまな問題に解決策を提案できる総合的視野と造形力を養います。
Q どんな未来が待っている?
卒業後は、デザイナーや専門家として家電・自動車・文具などの大手メーカーや広告代理店、デザイン事務所、広告制作会社のほか、ゼネコン、建築事務所など幅広い道への就職がひらけています。また、さらにデザインを追究する大学院進学という選択肢もあります。
ゼミテーマ(一部抜粋)
タイポグラフィ・エディトリアルデザイン/サイエンスデザイン・ネイチャーイラストレーション/ベーシックデザイン/プロモーションデザイン/グラフィックアート/ペーパークラフト/ブランディングデザイン/アートプロジェクト企画/CG・アニメーション/造形制作/UXデザイン・UIデザイン/ユニバーサルデザイン/エコデザイン/エルゴノミックデザイン/インダストリアルデザイン・プロダクトデザイン/建築・設計/空間・遊具/インテリアデザイン・環境/空間・照明デザイン