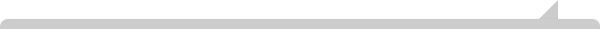学科紹介(歯学科)
歯学科
歯科医学を医学の一分科と捉えるオーラルサイエンス(口腔科学)で人間性豊かな歯科医師を目指す
学びの特色
- 教職員が一丸となった細やかな学修支援
- 付属病院との連携による実践的な臨床実習
- 患者に寄り添う全人的な歯科医師を育成
Q 日大松戸歯学部で何ができる?
口腔の健康は全身の健康を支えるという『オーラルサイエンス(口腔科学)』の学びを基に、社会の多様なニーズに対応できる高い倫理観を持った歯科医師を育成します。5年次の臨床実習ではSD(Student Dentist)診療室を開設。学生が指導医とともに患者さんのマネジメントを行いながら実践力を磨きます。
講座(一部抜粋)
感染免疫学/薬理学/病理学/歯科生体材料学/解剖学/放射線学/有病者歯科検査医学/保存修復学/歯周治療学/有床義歯補綴学/口腔インプラント学/小児歯科学/歯科矯正学/障害者歯科学/口腔外科学/歯科麻酔学/内科学/脳神経・頭頸部外科学
歯科医師国家試験合格率(新卒者)
| 第114回 (2020年度) |
第115回 (2021年度) |
第116回 (2022年度) |
|---|---|---|
| 81.8% | 55.6% | 74.2% |