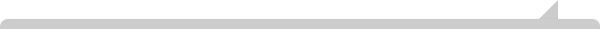バイオサイエンス学科
バイオテクノロジーで生命現象を解明し
深刻化する社会問題を解決する
 [スマートセルインダストリー]
[スマートセルインダストリー]微生物や植物の潜在能力を理解し、生物情報解析や
ゲノム編集技術等により高機能化するための実践的な知識を養います。
学びの特色
- 特徴的な3つのコース・緩やかなコース制
- バイオサイエンス×生物情報×デジタル技術
- 社会とのつながりを重視した教育と研究
Q バイオサイエンス学科で何をする?
人間をはじめ生物が持つさまざまな“はたらき”や“メカニズム”を、先端的バイオテクノロジーで解明し、社会に還元することで新たな産業を生み出すことを目的としています。健康で持続可能な快適なくらしを実現する技術の発展と創生に携わる人材を養成します。
Q どんな未来が待っている?
ヘルスケア・化粧品・医薬品・サプリメント・食品・香料・酵素・新素材の研究・開発に関わる企業や、バイオ産業に関係する企業・団体などで活躍するほか、中学・高校教員,国家公務員・地方公務員(技術職)、博物館の学芸員など、バイオサイエンスに関わるさまざまな分野で活躍できます。
研究室テーマ (一部抜粋)
栄養機能成分を用いた血栓症予防に関する研究/動脈硬化を防ぐ天然成分に関する研究/難治性疾患を改善する組換え体タンパク質の開発/発酵醸造微生物の特別な代謝機能の解析/産業廃棄物のメタン発酵による資源化/抗ウイルス剤の設計・合成・評価/酵素タンパク質の機能改変/硝化菌の培養法開発とゲノム解析/100℃で死なない微生物たち/植物の重金属ストレス応答/植物の記憶を形成する遺伝情報
動物学科
分子から生態系まで“動物の謎を解明する”
面白さに出会える
 [動物地理学]
[動物地理学]地域によって動物相や動物の分布が異なります。
この分布を決定づけている生態的要因と地理的要因について
進化学的視点から学びます。
学びの特色
- 生体機能×進化×環境×多様性を学ぶ
- 動物に関わる幅広い研究成果で多方面に貢献
- フィールド調査から最先端の実験まで網羅
Q 動物学科で何をする?
多様な動物種を対象として、それぞれの動物が有する特徴的な機能・かたちから、動物が示す行動や自然界での生態を学び、さらには進化の背景を探究します。その学びにより、自然環境や人間社会への対応を考え、実践できる人材を養成します。
Q どんな未来が待っている?
中学・高校教員や博物館の職員など教育関係の職種、学んだスキルを生かした環境調査やそのほか自然科学に関わる業種、医薬品・化学メーカー、出版・メディア関係などの企業、公務員などが期待されます。大学院へ進学して研究をさらに深め、研究者を目指すこともできます。
研究室テーマ (一部抜粋)
昆虫のユニークな生き方を探る/野生動物の生態・生態系機能を最新手法で研究/小型哺乳類の進化・生態・分類・動物地理/微生物による外来昆虫や農業害虫の抑制研究/ヒトと野生動物のより良い関係を目指して!/動物の行動や代謝など生理機能について研究/海岸生物からひも解く自然のしくみ/免疫と健康・病気の関わりを探る/昆虫の動物地理と生物多様性の把握/動物の行動や代謝など生理機能について研究/細胞分化や組織再生のメカニズムを解明する
海洋生物学科
海洋生物や海洋環境に関する幅広い研究で
海と人のくらしの調和を創造する
 [海洋基礎実習Ⅰ]
[海洋基礎実習Ⅰ]静岡県下田市に設置した臨海実験所で実習船などを利用しながら、
マリンフィールドサイエンスの基本的な知識・技術を身に付けます。
学びの特色
- 海洋生物について現場で深く学べる
- 水族館の最前線を学べる
- 海洋生物のスペシャリストを目指す
Q 海洋生物学科で何をする?
地球の7割を占める海には、多種多様な海洋生物が生息しています。海洋生物の多様性維持と食資源としての効率的な生産や利用について学び、海洋環境保全と持続的発展に不可欠な知識と技術を身に付けます。そして、人の豊かなくらしと海洋環境の調和を創造できる人材を養成します。
Q どんな未来が待っている?
卒業生は食品の製造・流通・分析・検査関連のほか、国家公務員・地方公務員(技術職を含む)、中学・高校教員、水族館、博物館、環境アセスメント、海洋関連研究機関、製薬関係、通信・情報関連、建設関連などさまざまな分野で活躍が期待されます。
研究室テーマ (一部抜粋)
鯨類の浸透圧調節とストレスに関する研究/水産生物の品種改良/フグの毒化機構/海洋生物からの医薬品シード化合物の探索/未利用海洋バイオマスの有効利用/捕食者誘導による表現系の可塑性に関する研究/海洋生物の代謝物動態/魚介類の病気の発生機序および予防/魚類免疫機構の解明/相模湾における沿岸海洋生態系の解明/魚介類の生活史特性および生息環境特性の解明/魚類の周波数弁別機構の解明/データロガーを用いた魚類の飛翔・産卵行動解析
森林学科
森林を多角的に研究し
持続可能な社会に役立つ森林の働きを学ぶ
 [きのこ学]
[きのこ学]きのこは身近なものでもありますが、生物としてのきのこを知っていますか?
きのこと森林との関わりからその実態に迫ります。
学びの特色
- 森の生物、森と人の関係、恵みの活用を学ぶ
- 森林を通じたSDGsに貢献する実践力を修得
- 森林生態系を守る仕事や樹木医も目指せる
Q 森林学科で何をする?
森林は人類の生存にとって不可欠な緑豊かな環境を提供してくれる存在であり、また地球上で最も現存量の多い生物資源です。森林生態系のしくみや人間社会との関わりを理解し、持続可能な社会の実現のため、森林の有効活用や自然環境の保全利用に関する課題と向き合う知識と技術を身に付けます。
Q どんな未来が待っている?
国家公務員(林野庁など)・地方公務員(林業職)として、森林を管理・保全する仕事に就いたり、民間企業では林業・造園、土木・緑化、環境アセスメント、住宅産業、建材加工・建設、紙パルプ・製紙関係、測量関係、森林関係のコンサルタントなど、森林分野に関連するさまざまな業界で活躍が期待されます。
研究室テーマ (一部抜粋)
森と木の健全性に関する研究/生物の相互作用と多様性の関わり/森林の物質循環と生態の解明/きのこのユニークな生態と働きの謎/山と森をめぐる水の移動/森林と社会をつなぐ仕組みと教育/森と気象の深い関係/未来の森づくりを考える/基盤資源としての森林バイオマスの活用技術/サステナブル住宅のあり方/森の恵みによるインテリア空間デザイニング/樹木や文化財の調査から歴史を辿る/森から生まれる新素材を探す
環境学科
地球規模で発生している環境問題の
解決方法や自然環境の保全について学ぶ
 [環境学概論]
[環境学概論]私たちを取り巻く環境。
より良い未来を目指すために、まず何を知るべきか?
その扱い方や測定方法などの基礎的な知識を学びます。
学びの特色
- 地球環境・自然環境・都市環境を学ぶ
- 環境に関する多様な課題を科学的視点から解決する
- 環境問題の解決に向けた実践力を修得する
Q 環境学科で何をする?
現在、国際社会の大きな課題となっている環境問題について学びます。その内容は、地球環境や自然環境から食料生産、資源循環、都市・住居環境まで広範囲に及びます。広い視野とグローバルな視点を備え、人と自然の共生環境を保全・修復・創造できる“確かな人材”を養成します。
Q どんな未来が待っている?
環境調査や分析に関わる仕事、環境に関わる公務員、建設・造園・まちづくり・防災に関わる仕事、環境計画コンサルタント、教員などでの活躍が期待できます。また、企業の環境配慮行動が必要とされる今、あらゆる業種で環境学科の教育内容を修得した人材が求められています。
研究室テーマ (一部抜粋)
地球温暖化と生態系変化/大気や降水の化学成分/乾燥地の砂漠化対策/土壌・水環境の修復保全/人と自然の共生できる緑地造り/流水中の窒素・炭素の動態/湿地の環境保全と活用/流域の窒素・リンの循環/汚染土壌と土壌酸性化の対策/野生動物と環境の保全医学/水環境の維持形成/野生植物の保全と資源活用/環境政策の経済的評価/環境配慮型材料の開発・実用化/環境と共生する都市づくり
アグリサイエンス学科
生命科学の知識と先端技術を修得し
食料生産やフラワー装飾のスペシャリストへ
 [アグリサイエンス基礎実験]
[アグリサイエンス基礎実験]最新の施設で動植物を生産し、花やフルーツ、ミルクなどの
ブランド農産物とは何かを科学的に解析します。
学びの特色
- スマート農業と生命科学で未来の農を創る
- 農産物高付加価値への科学的アプローチ
- フィールドからアグリバイオまでを学ぶ
Q アグリサイエンス学科で何をする?
生命科学のさまざまな理論を学び、キャンパス内のフィールドでは作物生産や動物飼育などの技術を修得します。理論→実践→検証の相互循環型学修から、価値の高い植物・動物性食資源を生産し、安定的に供給するしくみの構築や、多様化する消費者ニーズに対応する能力を養成します。
Q どんな未来が待っている?
地域ブランド食品関連企業、食品企業の農産物部門、食品メーカー、サービス業などの食品関連の仕事のほか、フラワー装飾、種苗の開発、農薬・肥料に関する仕事、農業資材関係、農業法人、造園業、農産物の小売・市場といった植物に関わる業界などで活躍できます。国家公務員・地方公務員や中学・高校教員も目指せます。
研究室テーマ (一部抜粋)
根域制御による植物栽培/器官形成遺伝子解析/日持ち植物の作出/ニーズに合った品種・技術改良/野菜や豆の高品質化/非破壊による青果物の品質評価/種子休眠形質の遺伝解析/地域研究手法による農業技術改善/光学による作物状態“見える化”/作物の香り成分合成機構の解明/おいしさを引き出す作物栽培/特定生物による環境浄化や病虫害防除/反芻家畜第一胃内微生物の飼料消化と発酵特性/ブタ精子の受精能力評価/反芻動物の栄養管理
食品開発学科
人の健康の維持・増進に役立ち
安全な新食品を開発する力を養う
 [食品開発演習]
[食品開発演習]これまでの講義などで修得した知識とグループワークを通じて
新しい食品を企画・立案し、実際に皆さんの力で完成と実現化に挑みます。
学びの特色
- スマート農業と生命科学で未来の農を創る
- 農産物高付加価値への科学的アプローチ
- フィールドからアグリバイオまでを学ぶ
Q 食品開発学科で何をする?
食品開発の基盤となる基礎理論、食品の機能や栄養に基づく人の健康及び衛生・分析技術に基づく安全管理といった食品づくりに関わる科学的知識と技術を修得し、未来を見据えた食品の創造開発を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。
Q どんな未来が待っている?
食品、香料、化学、医薬品などの製造業や食品研究機関における開発者・研究者、食品卸や小売業など広く食品業界での活躍が期待されます。そのほかにも食品衛生や食品分析関係の公的機関・公務員、中学・高校教員などが有力な進路となります。
研究室テーマ (一部抜粋)
食品の冷凍保存による内部構造への影響に関する研究/乳酸菌の抗菌物質・代謝産物の特性評価と食品保存剤の開発/う蝕予防効果を有する新規納豆の開発/腸管免疫系のしくみと腸内細菌や食品に注目した研究/食品の香り成分の嗅覚刺激による生体機能への影響に関する研究/食品成分の新規分析法の開発/酵母が産生する攻撃物質や防御機構および相互作用に関する研究/光や圧力を利用した食品の非加熱殺菌法の実用化を目指した研究
食品ビジネス学科
食の世界を多様な視点から深く探究し
食品ビジネスの新たな担い手を養成する
 [フードコーディネート実習]
[フードコーディネート実習]新商品の企画立案、テーブルコーディネート、料理写真の撮影法、
プレゼンなどをもとに食品ビジネスを実践的に学びます。
学びの特色
- 食に関する課題を解決し新たな未来を創造
- 最先端の食品ビジネスの現状を体験的に学修
- 企業のトップによる食品ビジネス特別講義
Q 食品ビジネス学科で何をする?
食料資源・環境、食品産業、食文化・食品科学を柱に経済学・経営学・社会学・調理科学などの視点を取り入れ、日常的な問題から地球規模の食料問題まで食に関する多くの課題を掘り下げます。あわせて新たな食品ビジネスの担い手になるための企画力・プレゼンテーション力を身に付けます。
Q どんな未来が待っている?
多くの卒業生が食品・飲料・菓子製造業や、生産現場と消費者を結ぶ食品流通業、多様な食を提供する外食産業など、食品関連企業に就職しています。 また食品製造・加工会社の後継者となる卒業生もいます。フードスペシャリスト、フードコーディネーターといった専門資格も食の現場で役立ちます。
研究室テーマ (一部抜粋)
イノベーションと食品企業/食品企業の戦略と消費者行動/食品ロスとSDGs/国境を越える食と貿易ルール/国産農水産物・食品に期待される役割/フードシステムの拡大と食リテラシー/食ビジネスと地域活性化/超高齢社会に適した食品物性/おいしさの秘密に迫る官能評価/食文化を対象とした観光/生鮮農産物の生産・流通/嗜好性を向上させる香り/安全な食料生産と有機農業/地球温暖化と食料生産/農山村及び離島の地域振興
国際共生学科
多様化するグローバル社会で,
しなやかに力強く活躍できる人材を養成する
 [国際共生学ゼミナールⅠ・Ⅱ]
[国際共生学ゼミナールⅠ・Ⅱ]グローバル化・多様化時代の生物資源に関する
諸課題と分析方法を学びます。フィールドワークを含む
課題解決型プロジェクトを立ち上げ解決策を探ります。
学びの特色
- グローバルな視点でビジネスや文化を学ぶ
- 国内外での“体験”を通じて学べる
- 次代に必要とされるコミュニケーション能力が身に付く
Q 国際共生学科で何をする?
生物資源と人との共生、生物資源の生産国・利用国との国際共生を図り、生物資源を国際的にマネジメントできる人材の養成を目指します。そのために、グローバル化・多様化の時代に不可欠な『多角的な視点から国際的な共生を図ることができる知識・思考力とその実践力』を学際的に学修します。
Q どんな未来が待っている?
生命・食・環境に関する生物資源の貿易、流通、サービスに関わる仕事や、観光関係、商社、金融・保険、不動産、建設関係、通信・情報に関連する企業や団体など、さまざまな分野で活躍できます。国家公務員・地方公務員や中学・高校教員、大学院進学も目指せます。
研究室テーマ (一部抜粋)
国際貿易に関する課題への対応/資源循環による地域の持続的発展/日系企業のグローバル戦略/持続可能なフードシステムの構築/生物資源の有効活用と適正管理/空間の文化的共通性と多様性/人類共通の価値の追究と実現/多文化共生による平等と公正の実現/自然生態系管理の構造の解明/農業・農村開発による国際協力/言語や文化による共生社会の実現/データサイエンスによる生物資源の分析
獣医保健看護学科
獣医師と協働して動物の健康と福祉に
貢献する愛玩動物看護師を目指す
 [動物看護学総合実習]
[動物看護学総合実習]付属動物病院には最先端の施設、優れた教員とスタッ フが配置され、
豊富な症例(犬猫)に触れながら、基本からしっかりと学びます。
学びの特色
- 動物の福祉と愛護を考える
- ヒトと動物の関係を紐解く学び
- チーム獣医療のスキルを身に付けるカリキュラム
Q 獣医保健看護学科で何をする?
動物の健康管理や看護に必要な専門知識と技術を幅広く学び、動物の診療補助や適正な飼養、疾病の予防からリハビリテーション、公衆衛生まで、動物管理における実践的な対応力の修得を目指します。また付属の動物病院と連携した実習を通じ、高いスキルを持った“愛玩動物看護師”を育成します。
Q どんな未来が待っている?
動物看護師として、動物病院で働くことはもちろん、動物関連産業(ペット保険、ペット飼料、動物書籍出版など)や動物臨床検査を行う医科学研究機関、実験動物施設、医療器機メーカー、製薬、医療関連のサービスを手がける企業・団体などで動物管理の知識を生かすことができます。
研究室テーマ (一部抜粋)
動物の形態・機能学的研究/病気の予防/人獣共通感染症の予防対策/内科疾患の看護学/外科疾患の看護学/動物の臨床検査学/動物と人が快適に暮らす環境作り/犬猫の適正飼養環境としつけ
獣医学科〈6年制〉
動物医療を通して動物と人の福祉に貢献
幅広い領域に対応できる獣医師を目指す
 [小動物外科学実習]
[小動物外科学実習]小動物外科学実習では犬や猫などの小動物を対象として、一般腹部外科
ならびに整形外科の麻酔や手術手技に関して実習を行います。
学びの特色
- 学修・研究をサポートする充実した設備と環境
- 高度獣医療を体験できる動物病院での臨床実習
- 人の医療への貢献も期待できる多彩な先端研究
Q 獣医学科で何をする?
獣医学科では、動物の健康維持・増進を図るとともに人の健康と福祉に貢献できる獣医師を育成しています。生命活動のメカニズム、病気の診断・治療・予防、公衆衛生、野生動物の保護や環境保全など広い領域をカバー。また、他学科や他学部との学際領域の共同研究にも積極的に取り組んでいます。
Q どんな未来が待っている?
卒業生の半数以上が伴侶動物、産業動物などの治療を行う臨床獣医師の道を選択。そのほか国家公務員・地方公務員として専門業務を担う獣医師、動物・畜産、製薬・食品関連の研究職、農業団体や動物園の獣医師など幅広い分野で活躍しています。また、例年1割弱の学生が大学院へ進学しています。
研究室テーマ (一部抜粋)
動物の比較形態・機能学的研究/動物生体内の分泌メカニズムの解明/動物の病気のメカニズムの解明/動物の生体防御機構の解明/野生動物における人獣共通感染症の疫学解明/人獣共通寄生虫感染症の病態と疫学解明/伴侶動物の疾患の正確な診断法や効果的な治療法の探索/横断的診察法の開発に関する研究/再生医療の動物医療分野への応用
獣医師国家試験合格率(新卒者)
| 第72回 (2020年度) |
第73回 (2021年度) |
第74回 (2022年度) |
|---|---|---|
| 94.8% | 92.0% | 87.1% |